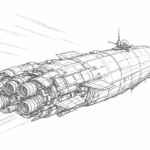虚空航路(The Void Route)
──私たちは、帰るために旅立った。
巻の一 第一章 臨界 ― Critical Point
高橋 遙過
時間を越えろ。希望はまだ、虚空の向こうにある。
プロローグ
赤茶けた岩山の稜線の隙間から差し込む、細く鋭い光がマルコの両目を射貫いた。
夜明けだ。
マルコは一瞬目を細めたが、それでも一心に前方を見つめる視線は外さなかった。
複雑な山肌の岩陰に乱暴な朝の光は一端身を潜めたが、やがて何者にも邪魔されることのない高みにまで昇ってくるだろう。
今日もまた暑く厳しい一日が始まる。
マルコは普段ならとっくに大人たちと一緒に狩に出かけている時間だった。
夜が明ける大分前に出発して「やつら」を襲い食料を奪った後は、岩場に掘った塹壕で日差しを避けて休息する。そして日が弱まった日没に食料と水を携えて「ホーム」に戻る。
普段ならすでに狩りを終え、岩場で休息をとっている頃合いだった。
マルコは岩陰から再び顔をみせた鋭光に、目を細めながらも食い入る用に前方を見つめた。
だが、今日は特別だ。
大人たちにホームに残る許可も得た。
しかし、完全に太陽が上空に昇りきるまでには片をつけなくてはならない。
時間がかかりすぎると、外で活動することが困難な時間帯に入ってしまう。
マルコはちらりと右前方に目をやった。
巨大な城のような黒い塊が、昇り行く太陽の光を反射して一瞬白く輝く。「シティ」の方角だ。
巨大な都市、そこには一時は何十万とも何百万ともいわれる人間が暮らしていたという。
しかしマルコはその話を信じていなかった。
そんなにたくさんの人間が存在していたなんて、マルコには到底受け入れられない概念だった。
あそこに人間は住んでいない。少なくとも今は。マルコはそう信じていた。
実際何人もの大人たちが「シティ」に向かったが、岩山のような鉄の残骸があるだけで、誰一人その内部に入ることはできなかったという。
しかし「やつら」は別だ。どこからかは分からないが何らかの方法であの「シティ」に出入りしているに違いない。マルコはそう信じていた。もしかしたら空からかもしれない。
マルコは祖父から、空を飛ぶ不思議な物体の話を以前に聞いたことがあった。
「やつら」はあの「シティ」に出入りして、そして何かを企んでいる…
マルコは軽く首を振り、回想を断ち切った。集中だ。今は目の前のことに集中しなければならない。
マルコは両手に持ったツルハシを再度強く握り締めた。
お粗末な武器であることには間違いない。しかし、それでもあいつを追い払うことはできるだろう。
「あいつだ!こっちに向かってくる。いつも通り、時間ぴったりだ!」
突如、背後でバカラが叫んだ。
その場にいた13人全員の目がバカラに注がれ、そしてバカラの指差す前方を見据えた。
「見つけたぞ!今日は絶対にあいつをとっちめてやる」
バカラは興奮して手に持った双眼鏡を振り回しながら、木で組み立てた粗末な見張り台の上をぴょんぴょんと飛び跳ねた。
あんなに興奮して台の上から落ちなければいいがと、マルコは一瞬思ったが、諫める気にはならなかった。
バカラはメンバーの中では一番年下で、そして見張り役だ。
あいつが毎日同じ時間に同じ方向からやって来ることは、メンバー全員が承知の上だったが誰も何も言わなかった。
そう、あいつは絶対に許せない。まだ小さい、たった4歳のバカラの妹、ミライを傷つけたのだ。ミライはひどいケガで未だ生死の境をさまよっている。
マルコは振り返ると仲間の少年たちを見つめた。そして、ツルハシを高く掲げると激を飛ばした。
「いいか、みんな、それぞれの役割は分かっているな。必ずミライの敵を討つんだ。そして、今日こそあの邪魔な機械をぶっ壊してやるんだ!」
マルコに呼応して少年たちは持っていた武器を振り回し、あるいはこぶしをぐるぐる廻して口々に叫んだ。
「やるぞ!」
「敵をうつんだ!」
マルコはその姿を見て満足げに頷くと、再び前方を見つめた。
少年たちが持っている武器はマルコ同様、いやマルコよりはるかに劣るものばかりだった。
スコップや鉄パイプである。
マルコは16歳で、少年たちの中では一番年上だった。大人たちについて狩にも出ている。だからこの粗末な武器であいつに立ち向かうということが、どれだけ無謀なことかは良く分かっていた。
ミライがやられたという、吸引機のようなものに吸い込まれたらあっという間に一毛打尽にされるということも。
前方の赤茶けた大地から四角い巨大な黒い機械が、白い粉塵を巻き上げながら進んでくるのが肉眼でも十分確認できるようになった。
マルコは前方を見据えたまま左手を軽くあげて合図をした。
5人の少年たちが後ろに下がり、「ホーム」の入り口を守る体制に入った。
だが、扉が開く音は聞こえない。
マルコは振り返り、叫んだ。
「バカラ!ホームに戻れ!」
「嫌だ!僕も妹の敵を討つんだ!」
バカラは見張り台から降りようとしなかった。
「ダメだ!そういう約束だぞ!」
マルコは再び叫んだ。
しかしバカラはぎゅっと口をつぐんだまま前方を見つめるだけだった。すでに双眼鏡は手から放して背中に背負っている。手には小さな角材をつかんでいた。
「バカラ!」
マルコはもう一度叫んだ。しかしバカラは微動だにしなかった。
「マルコ、仕方がない。個人の意志は尊重される。たとえそれが8歳でもだ」
隣でユルクがささやいた。
ユルクは15歳でマルコとは一つ違いだ。少年たちの中で二番目に年長のユルクも、来年にはマルコと共に大人たちに混じって狩に出る。
マルコは小さくため息をついた。
仕方がない。だが、何かあったときの責任は、一番年長であるマルコ自身が背負わなければならない。
「バカラの気持ちを組んでやってくれ。頼む」
ユルクが再び口を開いた。
マルコは頷くしかなかった。バカラの気持ちは痛いほどよく分かる。
あの巨大な機械の吸引機に、妹が吸い込まれる瞬間を目の前で目撃したのは、ほかならぬバカラ自身なのだ。
妹が機械に飲み込まれたことに気付いたバカラは、機械に殴りかかった。
機械はすぐにミライを吐き出したが、すでにその時、ミライの手足の骨は折れ、全身は傷つき血まみれだった。
時間になってもホームの奥に、バカラとミライの姿が見えないことに気付いた女たちが、ホームから駆け出してきた時には、すでに機械の姿はなく、泣き叫ぶバカラと血だらけで横たわるミライが残されているだけだったという。
しかし、ミライの敵を討つために、あの巨大な機械をやっつけようというマルコの提案に、大人たちの態度は冷静だった。
あいつは毎日同じ時間にやってくる。
そして周囲をうろつき回り、ホームの扉を開けようと散々扉を引っかいたあと、開いたわずかな隙間から毒ガスを撒き散らすのだ。
ガスはホームの入り口一杯に広がり、その度に残っていた女や子供たちはホームの奥深くまで逃げ込まなければならない。
大人たちに混じって狩に出かけるようになってからは、すっかりそのことを忘れていたが、子供の頃はあのガスを吸い込み、具合が悪くなって何日も寝込んでしまったことがしばしばあった。
あの機械は僕たちを殺すために毎日やってきているのに違いない。少年たちの間ではその話が何度も話題に上っていた。
しかし、今回のような事件が起こったのは初めてだった。
バカラとミライは、日の出前の、ホームから外に出てゆっくりと遊ぶことができる束の間の時間を楽しむあまり、機械がやってくる時刻になっていたことに気が付かなかったのだ。
そしてあの機械があんなに恐ろしい武器を持っているとも思っていなかった。
あの巨大な機械は毒ガスをホームの中に振りまいていくもの、とだけしか思っていなかったのだ。
まさか人間を飲み込んで粉々に砕いてしまうとは!
巨大なホースで人間を飲み込み、ボロ雑巾のようにしてしまう機械。やっぱり、あいつは僕たち人間を殺すために、毎日ここにやってきているのだ。
マルコは何度も大人たちを説得しようとした。このままではここにいる全員がいずれ殺されてしまうと。
しかしその主張は聞き入れられなかった。
男たちは毎日狩に出る。
一日でも休めば、たちまち次の日には飢えに喘ぐことになるだろう。
女たちはホームの奥深く、地下にもぐり、水を手に入れ、わずかばかりの食料を育て、子供たちの面倒を見なければならない。
ミライの敵を討つためには人手が足りないことを、マルコも十分分かっていた。
大人たちの手は借りない、自分たちだけでやる。そう頑なに主張する子供たちを前にして、
「その意志は聞き入れられなくてはならない。たとえそれが子供であったとしてもだ」
そう告げたのは「おばば様」だった。
「マルコ!来たぞ!」
ユルクが叫んだ。巨大な四角い機械が目前まで迫っていた。
「行くぞ!」マルコはツルハシを高く掲げると機械に向かって突進した。
後から7人の少年たちが続いた。
あらかじめ築いておいた岩の砦の手前で、機械は少し方向を変えると歩みを緩めた。その瞬間、左右に回り込んだ二人の少年がそれぞれ巨大なキャタピラにすばやく鉄パイプを差し込む。
キャタピラはゆっくりと鉄パイプを飲み込んでいったが、やがてさらに速度を落とした。
「今だ!」
マルコの合図を期に、少年たちは巨大な機械の四角い背中に飛び乗った。
マルコは、その上を見回した。何か開口部か突起物か、とにかく弱点に当たるようなものがないか探したのだ。とりわけ吸引機本体を。
しかし、背中には何もなかった。
つなぎ目のようなものはあるが、ミライが吸い込まれたという吸引機のような巨大なパイプも、毒ガスを噴射するためのホースのようなものも、そこには見当たらなかった。
「ちくしょう!吸引機はどこだ!」
このつなぎ目のどこかに格納されているのか?
それとも側面なのか?
側面ならば、キャタピラを止めたアンドレとヨセフが調べてくれている。
しかし、格納されていて見えないとしたら? 背後から吸引されて一網打尽にされてしまうかもしれない。
まずは、吸引機を探して破壊してしまわなければならない。
毒ガスのほうは、何とかなる。
マルコは焦りと恐怖で目の前が真っ暗になった。
「ダメだ!見つからない!」
「どこかに格納されているのかも!」
機械の側面に回りこんでいたアンデレとヨセフが口々に叫んだ。
吸引機がどこから襲ってくるか分からない。
5人の少年たちは背中合わせでマルコを囲んだ。
「バカラ!来るな!」
ユルクが叫んだ。
マルコは、見張り台を飛び降り、小さな角材を振り上げ、こちらに向かって走ってくるバカラを見た。
「ちくしょう!」
マルコは再び叫んだ。そして力一杯ツルハシを振り下ろした。
こうなったら、たとえ死んでもかまわない、少しでもこいつを傷つけてやる。
マルコは何度もツルハシを振り下ろした。
いつの間にか周りを囲んでいた少年たちも手にしたスコップや鉄パイプを振り下ろしていた。
一点に向かって、ただ一点に向かって。こいつに穴をあけてやるんだ!
少年たちは手にしたお粗末な武器を振り下ろし続けた。
機械の背中は次第にたわみ、そして小さな亀裂が入った。
「やったぞ。もう少しだ!」
マルコはその小さな亀裂に向かってさらにツルハシを振り下ろした。
その時、キャタピラの動きを阻んでいた鉄パイプが粉々に砕かれ吐き出された。
キャタピラは再び機能を取り戻し、前進を開始した。
バリケード代わりの岩の砦は、その巨大な圧力で砕かれた。
急に動きの加速した機械の背中で、少年たちはバランス失いその場に突っ伏した。
「ちくしょう!」
もはやツルハシを振り下ろすこともできなくなったマルコは、機械の背中にうつぶせになったまま、猶も素手で亀裂を広げようとしていた。
「危ない!」
バカラの叫び声が響いた。
ドスン!
その時、大きな振動と共に巨大な機械が小さく跳ねた。そして少年たちの何人かがその衝撃で機械から転がり落ちた。
マルコは機械の亀裂に指を差し込み必死に体を支えた。
吸引機か?
マルコはぎゅっと目を瞑ったが、その後に聞いたのは思いもよらない言葉だった。
「おい、お前たち、こんなところで何をしているんだ?」
何をしているかだって?
マルコは前進する巨大な機械から振り落とされまいとその背中に必死でしがみついたまま、何とかその声の主の方を見上げた。
目の前に白い鎧(?)を来た人間(?)が立っていた。
機械がバリケードの岩を乗り越えようとするガタゴトとした振動に、振り落とされまいと必死で耐えている少年の前に、声の主は悠然としゃがみこんだ。
マルコは呆然と男を見つめた。
「ふざけるな!みれば分かるだろう!こいつをぶっ壊すんだよ!」
近くでユルクが叫んだ。
白い鎧の男は一瞬首をかしげたが、立ち上がり、空を見上げた。やがて薄っぺらいヘルメットの中見が金色に輝いた。
そして再びしゃがみこむと、マルコたちがつけた小さな亀裂に指を突っ込み、そのまま、一気に装甲を引き剥がした。
マルコは驚いて亀裂から手を放した。
男はマルコの手が離れたところに再び指を掛け、そして再度一気に反対側に引き剥がした。
マルコがあけた小さな亀裂は、すでに大きな破れ目になっていた。その中は大きな機械と小さな機械が入り混じった複雑な形状になっていた。
これが、機械の中身なのか!マルコは目を丸くした。
正直なところ、マルコは機械の中身を見たのはこれが初めてだった。毎日ホームにやってくるこいつと、狩の時のやつ。大人はこいつらを機械と呼ぶ。
しかし、機械というものがどういうものなのか、マルコは本当には分かっていなかった。ホームの中には、少なくとも大人たちの言うような、勝手に動き回る機械などというものはなかったのだ。
白い鎧の男はむき出しになった装甲の中を確認すると、いくつかの小さな機械の間に手を突っ込んで何かをしたように見えた。
そして、巨大な機械はブーンというかすかな音と共に完全に動きを止めた。
マルコと13人の仲間たちはホームの扉の前で白い鎧の男を囲んで立っていた。
「お前は何者だ?」
「どこから来た?」
「僕たちを助けに来てくれたんだよね?」
少年たちが口々に質問を浴びせる。
白い鎧の男は堪忍したとでもいうように両手を軽く挙げると、少年たちの質問を全て無視して言った。
「僕はこの中に用がある。君たちの誰かが責任者なのか?もし、他に責任者がいるのなら面会を申し入れたい」
少年たちは顔を見合わせた。そして全員の目がマルコに向けられた。
マルコはユルクに目配せした。ユルクは頷くとホームの中へ入っていった。
それからしばらくの間、少年たちは白い鎧の男を取り囲んだまま、まんじりともせずに立っていた。
誰もが何か言いたそうに白い鎧の男を見つめていたが、男はまるで少年達の存在に気づいていないとでも言うかのように、そっぽを向いて立っていた。
マルコはすでに高く昇りつつある太陽を感じていた。
もうすぐ時間になる。直に高く上った太陽の熱で大地は灼熱の地獄と化す。すでに少年たちは太陽の熱で気化する、土中の液体の濃厚な臭気を感じていた。
これ以上ここにいるのは危険だ。急いでホームの中に避難しなければならない。
白い鎧の男は一人悠然とあたりをもの珍しげに眺め回していた。とりわけ、遠く聳え立つ黒い影のような巨大な城「シティ」を。
なぜ、この男はこんなに悠然としていられるのだろう?
じりじりと肌を焼く日射しとだんだんと濃くなっていく臭気に、子供たちはゼイゼイと息を上げ始めていた。
この白い鎧のようなものに秘密がある。マルコは思った。
灼熱の太陽も、強烈な悪臭も、この鎧のおかげでなんともないのだ。
もしかしたら、ヘルメットの中に発光した金色の光も、指先一本で機械の装甲を引き剥がした力も、全てこの白い鎧のせいなのかもしれない。
もしかして、「シティ」から来たのか?
その昔、何十万、何百万という人間が住んでいたという、あの「シティ」に今も人間が住んでいるのか?こいつのような人間が?
マルコはぞっとした。シティには誰もいないと信じていた。もし、そうではないとしたら?
マルコは迷った。この男に質問をするべきなのか?
その時、ホームの扉が開いた。
扉の前にはユルクが一人で立っていた。
「おばば様が面会するそうだ」
白い鎧の男はユルクに続いてホームの中に入っていった。そして少年たちも後に続いた。
ホーム入口から入ってすぐの扉の奥にある、広いホームの中でもとりわけ広い空間、通称「集会場」におばば様は立っていた。
マルコは集会場を見渡した。人がいない。
普段なら駆け回る小さな子供たちと、その面倒を見る老人たちであふれているはずの空間が、今は誰もいなかった。
おばば様が人払いを?
もちろん、マルコが知る限り今までにそんなことは一度もなかった。
ホームでどんな些細なことを決める時でも、大人たちと、そして、多くの知恵を持つ老人たちが席を外したことなどこれまで一度もなかった。
何か重要なことがおきている。マルコは思った。
おばば様は神妙な声で話し始めた。
「マルコ、皆。ユルクから話は聞いた」
おばば様は少年たち一人ひとりの顔を順に見つめた。
「お前たちの決断は讃えられるべきであり、その行動は勇敢である。今回の結末については男たちが狩から戻った後、公の席で発表される」
マルコとユルクを除く少年たちは皆安堵の微笑を浮かべ、とりわけバカラは飛び上がって喜んだ。
おばば様はにっこり微笑むと
「さあ、バカラ、こんなところにいてもいいのかい?お前が一番に行かなきゃ行けないところがあるんじゃないのかい?」
と、やさしくバカラに声をかけた。
バカラは飛び上がると、おばば様に丁重にお辞儀をして、そして一目散に集会場を出て行った。
その様子は少年たちを和ませた。
マルコも今日初めてともいえる微笑を持ってバカラを見送った。
おばば様は続けた。
「さあ、お前たちも今日は夕食までゆっくりお休み。大変過酷な試練を乗り越えたんだからね」
少年たちはおばば様にやはり丁重なお辞儀をすると、集会場を立ち去った。
後にはマルコとユルク、そして白い鎧の男が残った。
「ユルク、お前の意見は良く分かった。しかし、ここから先は私、おばば自身の経験を持って決断をさせてもらおうと思う」
マルコはこんな深刻な顔をしているおばば様をみたのは初めてだった。
ユルクはちょっと不満げな表情を浮かべたが、やはり丁重なお辞儀をして、何も言わずに集会場を出て行った。
やはり、これだけでは済みそうにない。
マルコはそっと目をつぶった。
この白い鎧の男の出現が何であれ、自分のしでかしたことの責任は大きい。
自分を含め14人もの少年たちの命を危険にさらしたのだ。
このホームに住む、いや自分の知る限りこの世界に生きる人間は二百人にも満たない。
男たちは仲間たち全員の生命の源である食料を得るために、毎日狩に出る。
女たちも、それぞれ子育てや水汲み、わずかばかりの食料の生産などにいそしんでいる。
そして働けなくなった老人たちは、これまで蓄えてきた知恵で子供たちに教育を施し、今、ミライを看病しているように、医療や健康にも携わっている。
そして残りの数十人がまだ狩に行くことが出来ない小さな子供たちだ。
今後ホームを支えていかなくてはならない子供達なのだ。
マルコは頭をたれた。
今回は誰欠けることなく、無事、機械を止めることが出来たが、それとて自分の力ではない。この白い鎧の男が空から落ちてこなければ、一体今頃どうなっていたか。
じっと頭を垂れるマルコをおばば様は優しく見つめた。
そして、男の方へ初めて向き直った。
「で、あんたはどこから来たんだい?シティからかい?」
マルコはぎょっとして目をあけた。
そして男の反応を確かめようとしたが、ヘルメットが邪魔して表情は確認できなかった。
男は肩をすくめ、簡潔に、そして無造作に答えた。
「そうとも言えるし、そうでないとも言える。しかしそれはどうでもいいことだ。僕はこの施設の地下奥深くにあるものを貰いに来た」
マルコは目を丸くした。このホームの奥深くだって?
女たちが採取するわずかばかりの水に?わずかばかりの食料に?興味があるとでもいうのか?こいつはホームを乗っ取ろうとでもいうのか?
マルコは白い鎧の男に歩み寄った。
こんな、信じられないような力を持った男が、わざわざそんなことでホームにやってくるとは思えない。しかし、確かに、この男は貰いに来たと言った!
今この場でホームを守れるのは自分しかいない。マルコは腰元から小さなナイフを取り出すと、白い鎧の男の喉下に突きつけた。
しかし、そんなマルコの覚悟とは裏腹に、白い鎧の男はまたもや、堪忍したよとでもいうように、軽く両手を挙げてみせた。
マルコはカッとした。
こいつの顔を生で拝んでやる!
マルコは男のヘルメットを引き剥がそうとして手をかけた。
しかしその瞬間、男のヘルメットの内部が金色に光り、そして、電気のような強烈な刺激がマルコの全身を貫いた。
マルコはこれまでにない衝撃に驚いておばば様を仰ぎ見た。
「のほほほほほほほほほ…」
おばば様はこれまでに聞いたことがないような、巨大な音量で笑った。
マルコは一瞬、おばば様の顔をみて凍りついた。
それは今まで見たことのない表情だった。
何が起こったのか分からない状況のうちに、マルコはおばば様の顔にいつものにこやかな表情が蘇るのを見た。
「白い鎧の男よ」
おばば様は厳かに言った。
「ついておいで。お前の求めるものをやろう。もとよりワシらには無用の長物。むしろ厄介払いしたい位のものだったしな」
おばば様はそう言うと集会場の奥の扉に向かって歩き出した。
マルコは慌ててその後を追った。
「マルコ。お前もおいで。ただし途中までじゃがな。お前も。私も」
手を貸そうとするマルコの肩をつかむとおばば様はマルコにそう囁いた。
細く曲がりくねった階段や長いスロープを抜け、おばば様はどんどんと地下深くへ下りて行った。そして、ゆっくりとした調子で後から付いていく白い鎧の男に、このホームについて説明をしていった。
おばば様が白い鎧の男にホームのことをあれこれと説明するのを、マルコは気に入らなかったが、おばば様には敬意を払っていた。
おばば様はホームの中でも一番の年長者で、長い長い先祖から伝わる伝承、物語の類を全て暗記している人物でもあった。
少年達の間では伝説などと笑い話の種にされることもあったが、大人達は、それを歴史と呼んで尊重していた。
おばば様のいう歴史というものが、マルコには完全には理解できなかったが、それが真理であるということが本能的に感じられる年頃になってきたのだ。
マルコはおばば様と親密に話をしている男の挙動から決して目を放さずに、二人の後を付いていった。
だから、この迷路のようなホームの地下で、いつの間にか未知の領域に入っていることに気が付いたのは随分経ってからだった。
おばば様はとある小さな扉の前で立ち止まった。
「ここから先は、動力を使わねばならぬ。動力はとてもとても貴重でな。われわれは普段の生活ではその一部も使ってはおらぬ。しかし、この先地下深くではその貴重な動力を無制限に使っておる。我等もそれを傍観している。その理由は分かるな?」
白い鎧の男は小さく頷いた。
「その貴重な動力をわし等の生活に使うことが出来たらどれだけ楽になるか…と、思うこともしばしばじゃが」
おばば様はそう言うと、扉の脇にある小さなパネルの前で、いくつかの作業を行った。
「確かに、この先地下深くには巨大なエネルギーとも言えるものが眠っておる。あんたの目的はそれだろう?わしらもそれを使うことができればどれだけ多くのことができるか…しかし、少なくとも今のわしらにはどうすることもできん。かといって放置しておくこともできん。そのまま、大切に保存しておくことしかできんかったのじゃ」
おばば様はそう言うと振り返って男に言った。
「そして、その保存のために大量の動力を使っておる。わしらに必要な少量のエネルギーさえ極度に節約しなければならないほどにな。この奥にあるものはわしらにとっては無用の長物どころか、今では単なる厄介ものじゃ」
白い鎧の男は黙って頷いた。
やがてウーンというかすかな音がした後、目の前の小さな扉が自動的に開いた。
マルコは一瞬たじろいだが、おばば様と白い鎧の男は何事もなかったかのように扉の中の小部屋に進んだ。
マルコは慌てて後に続いた。
扉は勝手に閉まり、そして小刻みな振動が続いた。
息詰まるような小部屋の中で、マルコは頭が揺さぶられるのを感じてすっかり気分が悪くなっていた。何だか分からないが自分のいるこの小さな部屋が動いているのを感じてすっかり動揺していたのだ。
マルコは初めて経験する動揺を二人に知られまいと努力した。
やがて頭に何かが浮遊するような感覚があった後、軽い振動と共に扉が開いた。
そこには細く長い空間がずっと奥まで続いていた。
低い天井の簡素な空間は、ホームのどの場所とも同じように両側の壁が崩れかかってはいたが、その壁には小さなドアがいくつも並んでいた。
動く小部屋を出ると、おばば様と白い鎧の男はどんどん先へと進んでいった。
マルコは初めて訪れる、ホームのこれまでに知らない一面に恐れを感じて、二人の後を追うのが精一杯だった。
おばば様は丸い巨大な扉のようなものの前で立ち止まると、白い鎧の男に問いただした。
「この扉は、ワシらには開くことはできん。じゃがあんたがシティの人間なら、簡単に開くことができるだろう?」
白い鎧の男は、造作もないといった様子で扉に近づくと、扉の左側面の小さな箱を開け、何か操作をした。そして、再び薄っぺらいヘルメットの前面を金色に光らせた。
男はヘルメットの中身をパチパチと金色に点滅させたまま、おばば様のほうへ振り向き、挑戦的な質問をした。
「で、この扉を開くことが出来たら、この中のものは根こそぎ持って行っていい、ってことでいいんだよな?」
おばば様は黙ってうなずいた。
マルコはこの大事な場面での一問一答を聞き漏らすまいと、必死で耳を凝らした。
しかし、今日朝から続く緊張状態と、狭苦しい空間の息苦しさ、そして今まさに白い鎧の男が発する金色の輝きの不協和音で、足元から崩れ落ちそうだった。
おばば様を守らねば…マルコは必死で体をささえようとしたが、足元から崩れ落ち、しゃがみこんだまま気を失った。
しばらくしてマルコは目を覚ました。
目の前にはおばば様の青い瞳があった。
マルコはびっくりして居住まいを正した。
「ははははは…何を今更。あんたの世話をするのは慣れたもんだよ」
おばば様は高らかに笑った。
マルコは顔を真っ赤にしながらも、平静を保とうと努力した。
「大丈夫かい?あれは大量の電波を発するからね。慣れないものが近くにいると当てられるんだよ」
そういうおばば様はこともなげだった。
「あ。あいつは何処に?」
マルコは照れ隠しに勢いよく立ち上げると男の姿を探した。
おばば様は目の前にある巨大な丸い扉を顎でしゃくった。
「この中だよ。この扉の厳重な鍵をいとも簡単に破っちまった。やっぱり、カエサルのものはカエサルに。ってことなのかね」
マルコはきょとんとしておばば様を見つめた。
今日のおばば様は自分にはわからないことばかりをいう。まるで知らない人みたいだとマルコは思った。
「あはははははは…」
おばば様はまたもや、高らかに笑った。
「マルコ、悪かったね。こんなところまでつき合わせて。しかし、あんたは未来のリーダーだ。今日ここで起こったことはしっかりと目撃しておいてもらわねばならん。そして次の世代に語り継ぐ役目を負ってもらわねばならん」
マルコは驚いておばば様を見つめた。こんな物言いをするおばば様も初めてだった。
マルコのもの問い気な様子を尻目に、おばば様は丸い巨大な扉をさすっていた。
「長い、長い間、この中のものを守ってきた。もちろんわしら自身の身を守るためにな」
おばば様は振り返り、にっこりとマルコに微笑みかけた。
「だが、この中のものをあの男が全て根こそぎ安全に持ち去ってくれるのなら、わしらにとってはむしろ大助かりだ。もっとたくさんのエネルギーをわしら自身の為に使えるようになる。この中のものの為にではなくて、わしら自身の為にだ」
マルコはおばば様を黙って見詰めた。
状況はよく分からなかったが、とにかく今起こっていることは良いことなのだろう。おばば様のいうことに間違いはない。
マルコはおばば様に並んで扉の前に立った。この扉の奥で白い鎧の男が何をしているのかは知らないが、とっととホームから出て言ってほしいとマルコは思っていた。
しばらくすると丸い巨大な扉が音もなく開いた。
そして中から白い鎧の男が出てきた。たくさんの四角い箱を積んだ大きなカートとともに。
「あんたのご要望通り、この中のものは根こそぎもらったよ」
白い鎧の男は言った。
「もうこの中は安全なのかい?」
おばば様の質問に男は簡潔に答えた。
「もう一切の電力を供給しなくていい」
おばば様は満足げに微笑むと、今度はマルコにも理解できる質問をした。
「で、この大荷物はあんた一人で運びだせるのかい?」
「造作もない。ただ、もっと大きなエレベーターがあると助かるのだが」
白い鎧の男はそう言うと少し肩をすくめて見せた。
「それなら、こっちにあるよ。さっきとは違う場所に出ることになるがかまわないかい?」
おばば様はそう言うと、男の返事も聞かずにさっさと歩き出した。
「助かる。時間が惜しい。何しろこの状態では数時間しかバッテリーが持たないんだ。バッテリーが切れたらどうなるかは分かるだろ?」
白い鎧の男はそう言うとおばば様の後を付いていった。
マルコは白い鎧の男が饒舌に話すのを始めて聞いた。
マルコはおばば様の後ろをカートを押しながら付いていく男の横に並び、男の顔を伺い見た。
ヘルメット越しにはっきりとは見えなかったが、それは若い男だった。
マルコは驚いた。自分とそんなに年も違わないのではないか?5歳も離れていないかもしれない。
一体こいつはどこから来たのだろう?おばば様の言うようにシティから来たのか?シティにはこいつのような人間が他にも住んでいるのか?だとしたら?
マルコは先ほど迷っていた質問をすることにした。
「シティにはあんたの他にも人間が住んでいるのか?」
「さあ。あそこにまだ人間が住んでいるかどうか、それは分からない。確認に行きたいところだが、時間がなさ過ぎる」
「あんた、シティから来たんじゃなかったのか!」
マルコは驚いた。じゃあこいつは一体どこから来たのか?
男は少し難しそうな顔をしながら答えた。
「厳密にはあの都市から来たわけではない。昔はあそこに住んでいたが。何だろうな?つい最近まで住んでいたはずなのに随分昔のことのように感じるな」
マルコは白い鎧の男の言った言葉の意味を考えるのに精一杯になっていた。ともかくつい最近までこの男はシティで暮らしていたのだ。でも、今シティに人間が住んでいるのかどうかも分からないという。
大分遅れてしまったマルコたちの前方でおばば様が扉を開ける音がした。
大きな荷物と共に男が中に入る。マルコも続いて中に入った。
さっき言っていたエレベーターってやつか?
先ほど入った小部屋より大分大きかったが、気分が悪くなったあの小部屋と同じものだとマルコは気がついた。
「さっきよりは大分時間がかかるよ。マルコ、大丈夫かい?」
ちょっと茶化したような調子でおばば様が言った。
マルコは何故だか恥ずかしさで顔が真っ赤になるのを感じた。
「なあに、すぐに慣れるさ」
男までもが楽しそうにマルコを見て笑った。
「大丈夫に決まってるさ」
マルコはそう言うときっと唇を結んで扉が閉まるのを待った。
やがて頭を押さえつけられるような感覚と共にエレベーターが動き出したのが分かった。
再び扉が開いて外に出た時、そこが広い部屋であることにマルコは気がついた。
しかし、ホームの中ではない。地上だ。ホームは地下に広がっている。しかしここは紛れもなく地上なのだ。
大きな部屋の崩れかけた壁のあちこちに大きな四角い穴が開いていて、そこから太陽の光が差し込んでいた。
「あんたたちはここでいいよ。外は危険だ」
白い鎧の男はそう言うとカートを押して広い部屋をまっすぐ進み、そして大きく開いた開口部から外に出て行った。
マルコとおばば様はその後姿をしばらく見送った。
マルコは男の後をついて行きたかった。男があの荷物を持ってどこに行くのか、自分の目で確認したかったのだ。
「マルコ、駄目だよ。外に出てはいけない」
マルコの気持ちを先回りして、おばば様が言った。
「一体あいつは、あの男はどこから来たんでしょう?」
マルコはおばば様に尋ねた。
「さあ。遠い未来からか、それとも過去からか」
おばば様は感慨深げにつぶやいた。
未来だって?過去だって?
マルコはカートを押しながら、夕日に照らされ長い影を作って歩いていく、男の後ろ姿を遠く見つめた。
いや、違う。あいつは今現在を生きている人間だ。僕たちと同じ人間だ。いずれ分かる日が来るだろう。あいつの持っている不思議な力の正体も。マルコはなぜかそう思った。
おばば様はマルコの肩に手をかけた。
「さあ、戻ろう。夕食までまだ少し時間がある。今日はゆっくりお休み。そして、明日からは歴史の勉強だ」
おばば様はすでにエレベーターの扉を開いていた。
マルコは急いでエレベーターに乗り込んだ。
「狩はいいのですか?」
そう尋ねるマルコに、おばば様はしっかりとした口調で答えた。
「狩よりももっと重要なことをお前たちは学ばなければならない。ようやくそれが出来るようになったんだからね。明日から何もかもが変わるよ」
エレベーターがゆっくりと動き始めた。
第一章 臨界 ― Critical Point
〝それ〟はまどろんでいた。
かすかなざわめきがそのまどろみを邪魔しようとしたが、
そんなことは良くあることで〝それ〟のまどろみを遮るものではなかった。
1 ナミ5歳
中空に昇った強い日差しが、一面のみどりの下に張られた水面に反射してキラキラとミノルの茶色く日焼けした頬をまぶしく照らした。
ふー、大きなため息をついて麦藁帽子を手に取ると、ミノルは首に巻いた手ぬぐいで額から滴り落ちる汗をぬぐった。腰にぶらさげた水筒から冷たい水を一気に喉に流し込む。貴重な水が体の隅々まで広がって、ミノルのほてった体を冷やしていった。
1号畝から9号畝まで、全て生育は順調だ。ミノルは満足げに一面のみどりを見晴らすと、再び大きな麦藁帽子をかぶりなおした。
古典的な農夫スタイルだが、ミノルはこの格好が気に入っていた。
ミノルは土にまみれてところどころ茶色くなった青いつなぎの大きなポケットから小さなノートパットを取り出すと、稲の発育状況を入力した。
他の区画のデータも確認する。全て順調。そう、暑すぎる以外は。
ミノルは農場を覆う蜂の巣状のガラス張りの巨大なドームを仰ぎ見た。強烈な太陽の日差しに目を細める。この日差しじゃあまだまだドーム内の温度は上がりそうだ。ノートパッドの片隅で激しく点滅するアイコンが危険を知らせていた。
気温 華氏93°F(摂氏35℃)、湿度60%
ミノルは少し考えた後、エアコンを調節する代わりに、ドームを覆うガラスを偏光させる指示を入力した。見る見るうちにドーム全体に満ちていた光が弱まった。いまや天井を埋め尽くす蜂の巣状のガラスは灰色く濁ったものになっていた。
これで今日一日は持つだろう。ノートパッドのアイコンはけたたましい点滅をやめ、おとなしいものに変わっていた。
次にミノルは今後の風向きと風速の予想データを確認した。
午後6時頃から数時間くらいなら風を入れられそうだ。
作物を順調に生育させるためにはなんといっても風が必要だ。それから、外の空気を入れて、中の熱を逃がしてやらねばならない。
ミノルは慎重にデータを吟味した。
おあつらえ向きの風向きだ。まだ各地に残っている火山灰や放射性物質も、この風向きなら飛んで来ないだろう。
ミノルはノートパッドにドーム全天を開放する予定時間を午後6時から3時間と入力した。
たとえ3時間とはいえ、全天を開放できる時間があるのは貴重だ。外から大量の風をドームの中に流し込んでやらなくてはならない。大量の風がなくては作物の根は丈夫に育たないのだ。そして丈夫な根が張らなければ、品種改良の末に一株あたりの生産量を最大限に上げた作物達は、その豊かな実りの重みで倒れてしまうだろう。
ミノルは眼前に広がるみどりの絨毯を再び満足げに見渡した。収穫の時期が楽しみだ。
今ミノルが立っている稲の区画の他にも、この農場ではとうもろこし、大豆、小麦、イモ類など数々の食物が育っている。区画は完全に分かれてはいるが、ミノルはバナナやオレンジ、オリーブなどもこの農場で育てていた。実際ミノルが育てている食物は実に100品種以上にものぼる。とはいえこのドーム内で育てているのは生育にどうしても土が必要なものだけだ。
土を使わない水耕栽培で生育可能なものはすべて、農場に隣接する水耕栽培塔で育てられている。土で育てるにはあまりにもスペースがもったいないからだ。
ミノルにとっては広大な農場とはいえ、その広さはわずか2ヘクタールほどにしか過ぎない。この程度の農場では都市に住む全ての人々の食料をまかなうことなど到底不可能だ。とはいえ、人々が合成ではない新鮮な食物を口にすることが出来る貴重な農場でもある。
ミノルはそれら全てを一人で管理していた。
最近ようやく詳細な気象予測データをもとに、農場を覆う、蜂の巣状のガラスの一部だけでも小刻みに開放できるようになっていた。
そのおかげで農場内部の温度や圧力調整のコストは大分削減されるようになってはいたが、それでも莫大なコストがかかっていることに間違いない。もっとも農場でかかるコストについてはミノルの管理するところではなかったが。
ミノルの祖父の時代、まだ地球環境がここまで破壊されてしまう前、閉鎖空間での実験農場として建設されたばかりの頃は、その温度と圧力の調整のためにそれはそれは巨額なコストが必要だったという。
ミノルはよく祖父の言葉を思い出す。
「外にいくらでも土地があるのに、なんでこんなにお金をかけてこんなところで食料を生産しなきゃならないんだ? と、昔は良く父親に食って掛かったものだが、それが今じゃどうだ?こんなところでしか食物が育たないようになっちまった。人間なにが幸いするか分かったもんじゃない。人間万事塞翁が馬ってやつだな」
祖父はこの農場が嫌いだった。
外にいくらでも緑の空間があると分かっているのなら、完全な閉鎖空間であるこの農場は窮屈でやりきれないものだったに違いない。ミノルは祖父の気持ちを推察する。しかし既に荒れ果てた世界しか知らないミノルにとってそれは難しいことだった。その祖父も今はもういない。
もともとこの農場はバイオスフィア2と呼ばれる巨大な実験施設だった。しかし本来の意味でのバイオスフィア2は今はあるべきところに移動されている。つまり、宇宙空間にだ。
巨大なドームで囲われたこのバイオスフィア農場は、幸いなことに酸性雨や放射能からも免れることができた。次々と巻き起こった異常気象や地殻変動からもだ。地上が汚染されてあらゆる食物が枯れ果てた後も、閉鎖的な空間が幸いして、この農場だけはなんとか生き残ったのだ。
閉鎖空間での実験農場のはずだったバイオスフィア2が、今はただの農場となり、健康な食物を育てる地上で唯一の空間になってしまったなんて、なんとも皮肉な話だ。地球が、その本来の力を取り戻すのはいつのことだろう?それともそんな日は永遠にこないのか?
ミノルは再びしゃがみこみ、稲に張られた水のサンプルとその下の土のサンプルを採取した。家に戻ったらサンプルを解析しなければならない。最近は簡単な解析作業などは農場にある実験施設の中ではなく、全て自宅の研究室で行うことにしていた。
自宅に妻と小さな娘を二人だけで置いておくことが少々心配だったのである。
ミノルはサンプルに小さなラベルを貼ると、慎重にサンプルボックスにしまいこんだ。
そこには既に今日採取した数十本ものサンプルが入っていた。
ミノルはノートパッドに短くデータ送信の指示を出すと、送信ランプの点滅が収まるのを見守った。ランプは小刻みに震えていたが、やがて送信完了のマークが画面に表示され、ノートパッドは暗くなった。
これで今日の作業は終了だ。ミノルは慎重にノートパッドをつなぎの大きなポケットにしまいこんだ。先ほど送った全てのデータは農場の中央に高く聳え立つ、中央制御塔の中に設置されている巨大なコンピュータで解析される。
データ分析におけるミノルの評価と行動はその中にあるAIの機械学習に大きなウエイトを占めるように設計してある。機械学習が飛躍的に進むにつれて、AIは的確な指示を各ブロックを担当するコンピュータに出してくれるようになっていた。おかげで、ミノル一人でも広大な農場と巨大な水耕栽培塔を一人で管理出来るのだ。
今ではミノルもAIに「ナギ」という愛称をつけて親しみをこめて呼んでいた。「ナギ」の為にも、ミノルはこの農場では模範的な行動を心がけていた。小さな子供が親の真似をして育って行くようにミノルも「ナギ」を育てていた。
「ナギ」とは「イザナギ」のことで、古い日本神話の創生の神の名前だ。祖父がよくミノルを抱いて話してくれた物語の中でも、ことにミノルの興味を引いた物語から拝借したのだ。
祖父は78歳まで、今思えば随分長生きをしたが、それでも今まだ生きていてくれたら、もうちょっとこの農場を愛してくれたかも知れないな、とミノルは思う。
普段は植物のDNAや根粒菌を調べているミノルだったが、実際この農場で食物を育てている時間の方がミノルにとっては好ましかった。この農場の中にはみどりがある。外の世界にはない全てがある。
サンプルボックスを乗ってきた自転車の前籠に載せると、ミノルはゆっくりと自転車を漕ぎ始めた。
そうだ、家に戻る前に水耕栽培塔を確認しにいこう。そろそろ新鮮なイチゴが色づいている頃だ。人類の為の貴重な食物資源ではあるが、生育状況の確認の為に一粒くらい口にすることは許されるのではないか?家で待っているサラとナミにも一粒ずつ持って帰ってやろう。サンプルボックスの中に入れておけば家まで持つだろう。
ミノルは新鮮なイチゴの甘い、みずみずしい味わいを思い返し、にんまりとした。そして稲の間の細い小道を全速力で駆け抜けた。
自転車が興す小さな風がミノルの汗をぬぐっていく。ミノルはこの原始的な移動手段も気に入っていた。なんといってもエコロジーだ。
稲の区画を抜けて中央制御塔への長い直線に入った時、ミノルはこちらに向かって走ってくる小さな人影に気が付いた。
「ナミ!」
ミノルは驚いてその人影に向かって自転車を走らせた。
「パパ!」
ナミは息を切らせながらミノルに駆け寄ると、ミノルの足に絡みついた。
「ママに送ってもらったのかい?」
ミノルはすがりつく娘の頭をなでてミノルの方に顔を向かせるとそう尋ねた。
「ううん。一人で来たの」
ナミは少し得意げに鼻をひくつかせた。
「悪い子だ。一人で車に乗ってくるなんて」
ミノルは少し、しかめっ面をつくってみせた。
「だって、簡単だもん。車に乗ってピッピッってやればいいだけなんだから」
ナミは口をとがらせた。確かにまだたった5歳のナミにとっても車に乗ってここまで来るのは簡単なことだろう。ナミの言う通り、ピッピッとやればオートパイロットでここまでものの数分で着いてしまうのだから。
ミノルがいつも行っている操作を隣で見ていていつの間にか覚えてしまったのだろう。この年頃の子供は何でも大人のまねをする。
でも。万が一途中で車を降りるようなことになれば、どんな事態が起こるか予想出来ない。どう言ったら一人で車に乗らないように教えることが出来るだろう?
「それでも悪い子だ。お前が車に乗って来てしまったら、ママがどこにも出かけられないだろう?」
ミノルは怒った顔をして見せた。
「ママはどこにも出かけないもん」
ナミは尚も食い下がる。
困ったな。ミノルは思った。確かにママはどこにも出かけない。昔はよくこの農場にナミを連れて来ていたものだが、あの宇宙船の一件以来すっかりふさいでしまって、家の中にこもりっきりになってしまった。
まだまだ何年も先の話で、計画がうんと遅れればミノルの代わりに他の誰かが行くことになるかも知れない話なのに。
「それでもだ。第一この広い農場で迷子になったらどうするんだ」
ミノルはナミを説得しようとした。
ナミはまた得意げな口調で言った。
「パパの場所なんてすぐに分かるよ。入り口に表示されてるから」
そうだった。この巨大な施設の入口には中にいる人間の所在が分かるように、その位置情報が表示されていた。ミノルは観念するしかなかった。
「ねえパパ!パパが乗るのはあの宇宙船?」
ナミが突然中空を指差した。
高い農場のガラス張りのドームの向こうに小さなシャトルが飛んでいくのが見えた。
「ナミ、あれは宇宙船じゃなくて、補給船だよ」
ミノルは笑った。
「知ってるだろう?宇宙エレベータを使って宇宙から運ばれてきた資源を都市に運んでいるドローンだよ」
ミノルはそう言うとかわいい娘の黒い髪を優しくなでた。
まだ年端も行かない娘は、いつか自分の父親が宇宙に行くかもしれないというだけで、単純に嬉しく、誇らしいのだ。いつか夫がいなくなってしまう、という思いで不安に駆られ陰鬱になってしまったサラとは違う。
いつか、この子も母と同じように寂しさで引きこもってしまうようになるのだろうか?
「ちぇっ。宇宙船じゃなくて補給船ばっかりね。宇宙船なんてひとつも見たことがないわ。本当にあるのかしら?」
ナミは口を尖らせた。
「はははは。パパの乗る宇宙船はとっても大きいんだ。だから、宇宙で建造されているんだよ。残念ながらナミには見るチャンスはないかも知れないな」
ミノルは少し意地悪げに笑うとナミを自転車の荷台に載せた。
「さあ、帰らないと、ママが心配する」
ミノルは自分の背中にしっかりと手を回す娘の手を軽く握ると、ゆっくりと自転車を漕ぎ始めた。
「ママは心配しないよ」
ミノルの背中でナミが言った。
困ったな。サラの欝がまた激しくなったのかな?早く戻らないと。ミノルは自転車をこぐ足を速めた。
ナミは続けた。
「パパとママの昔のお友達が来たの。だから私がパパを呼んでくるって、ママに言ったの。だからママはそのお友達と話をしているから大丈夫なの」
「何だって!」
ミノルは思わず自転車を止めるとナミを振り返った。
ナミは驚いて目を見開き、ミノルを見つめた。
今何と言った?昔のお友達だって?ミノルは驚いて尋ねた。
「昔のお友達が来たって、ママがそう言ったのかい?」
「そうよ。白いモバイルスーツを着た男の人と女の人。あれ、モバイルスーツっていうんでしょ?知ってるよ。この前ニュースで見たから」
ナミは再び得意げな顔をして答えた。
「だからママの代わりに私がパパを呼んで来るって言ったのよ」
ミノルはナミの目を覗き込んだ。
「本当は、ママの代わりに電話するって言ったんじゃないのかい?」
「だって、電話したらここに来られないじゃない?」
ナミはそっぽを向いて答えた。
「悪い子だ」
ミノルは今日3度目のセリフを口にした。
「さあ、急いで帰るぞ。ナミ、パパにしっかりと捕まれ!」
ミノルはそう言うと全速力で自転車を漕ぎ出した。
なんてこった!セリグとエレナが尋ねてきたんだ!何年ぶりだろう?メールや電話で連絡は取っていたが、実際に会うのは…十年以上ぶりだ!
ミノルはイチゴのことなどすっかり忘れていた。
ミノルの住む自宅は巨大な団地の一角にある。主に都市の外に研究所を構える科学者専用の居住スペースだ。
都市内では研究出来ないような、多少の危険を伴う実験を行ったり、ミノルのような巨大なスペースを利用しなければならないような科学者たちが集まり住む、いわば学術団地のようなものだ。
以前はそれでもたくさんの研究者たちが住んでいたが、都市での人口コントロールが進むに連れて、都市の狭い研究室でも事足りる科学者たちは次第に都市へと移動していった。
今ではこの巨大団地に住む科学者たちも大分減ってしまっている。
ちょっとしたゴーストタウンのようなものだ。
でもおかげで広々とした居住スペースと、ちょっとした実験や解析をするスペースを確保出来るのはミノルにはありがたかった。
ただ、ミノルにとって娘のことは気がかりだった。同じ年頃の、友達になれるような子供がいないのだ。
自分たちが子供の頃は、まだ人もたくさんいて、とりわけミノルと、今は妻となったサラ、そしてセリグとエレナは、他に年の頃の似た子供がいないこともあって、いつも一緒だった。
子供の頃はミノルの父親が管理するあの農場で良く一緒に遊んだものだった。
ミノルと一回り年の離れたサラはいつもミノルの後をくっついて回っていた。
ミノルと5つ違いのセリグとさらに2つ年下のエレナの面倒を見てやったのも、やはり一番年長のミノルだった。ミノルにとってセリグとエレナは可愛い弟と妹のようなものだった。懐かしい美しい思い出だ。
やがてセリグは父親の影響で工学博士となり、やはり両親の影響で医学博士となったエレナと結婚した。そして子供が産まれ、他の多くの学者とその家族が都市へと移動していったように二人も都市へと移っていった。
それ以来二人とは直接会っていない。
ミノルがサラと結婚したことも、ナミが生まれたことも電話で報告した。
都市と、この団地とでは、それほど行き来が難しいのだ。
すぐ近くにあるのに。
ミノルはナミを抱きかかえたまま、勢い良く玄関を開けると、家の中に飛び込んだ。
リビングには白いモバイルスーツを着た二人の姿があった。
ヘルメットのせいではっきりとは見えなかったが、それが懐かしい友人たちであることは間違いなかった。
「セリグ!エレナ!」
ミノルは二人に駆け寄り、三人は篤い抱擁を交わした。
「久しぶりだ。何年ぶりだろう!」
ミノルは言った。
「なんと、実に十五年ぶりだよ」
「映像で顔は見ていたが、実際に会うとなるとまた違うもんだな。ミノル、やっぱりお前、随分老けたぞ」
セリグが高らかに笑った。
「セリグ。あなたも同じだけ老けたのよ」
横からエレナがぴしゃりと言った。
懐かしい。二人とも全然変わってない。セリグの口の悪いところも、エレナのちょっときつい言い方も。
「どれ。この子がお前のかわいいナミちゃん。イザナミちゃんか」
セリグはミノルが抱えるナミに気付くと高く抱き上げた。
「かわいい子だ。この黒い目と黒い髪はミノルにそっくりだな。だが顔立ちはサラそっくりだ」
「あら、サラもきれいな黒髪と黒い瞳よ」
エレナも笑いながらナミの顔をのぞきこむ。セリグはエレナに向かってにやりと笑うと
「つまりは、サラにそっくりってことだな。これは大した美人になるぞ。 良かったなイザナミちゃん。パパに似なくて」
と言うと何度もナミを抱えあげた。
「なんだ、まだ会ってなかったのか」
ミノルは娘をほめられてまんざらでもなかった。
ナミはモバイルスーツの硬い腕に何度も抱きかかえられて不快そうに体をよじった。
「ママ!」
サラに向かって両手を伸ばす。
セリグは慌ててナミをおろして誤った。
「ごめんごめん。痛かったか?」
ナミはサラに駆け寄り、サラはナミを抱きあげた。
「いいのよ。ナミはそのスーツに慣れていないの。ずっとここで暮らしているから。都市の人間に会うのも初めてなの」
サラが申し訳なさそうに言った。
「いや、こちらこそ済まない。これでも大分良くなったんだけどな。まだまだ改良の余地がありそうだ」
セリグはナミとサラに頭を下げた。
ミノルは言った。
「そのスーツ、ぬいじまえよ。そしたらナミも嫌がらないさ」
「残念ながらそういうわけにもいかないんだ」
セリグはかるく肩をすくめて見せた。
エレナが後を続けた。
「都市病ってやつよ。思ってたよりかなり根が深いわ。さっきサラにも説明したんだけど」
「そうよ、せっかくお茶を入れたのに、二人ともお茶すら飲まないの」
サラが不服そうにこぼした。
テーブルの上には二つのティーカップが並んでいて、すでに中身は冷め切っているようだった。貴重な紅茶だ。サラがこぼすのも無理はない。
「都市へ移ってからすっかり免疫が後退してしまったのよ。この部屋のおそらくわずかなウイルスからも身を守ることが出来ないくらいにね。昔はへっちゃらだったのに」
エレナが悔しそうな顔をする。
セリグがため息混じりに言った。
「ほとんど無菌室のような状態で生活をしているからなあ。都市の中はほとんど無菌状態なんだ。ウイルスから身を守るため、そしてAIと量子コンピュータの誤作動を防ぐため。予測不能な事態を引き起こさないためにも、都市の中は徹底的に洗浄されているんだよ。それに比べたらここは菌だらけだ」
そういうとセリグは鼻に手をあてて〝くさいくさい〟というような仕草をして見せた。
ミノルとサラはそのおどけた仕草にくすくすと笑った。
「都市への出入りは厳重なの。そうじゃなくても火山灰やら放射性物質やら、都市の機能に著しい損傷を来たす要因が多すぎるでしょ? ごめんなさいね。本当はもっと早くに会いに来たかったんだけど」
エレナが申し訳なさそうに言った。
ミノルは都市と、それをとりまく過酷な現状を改めて思い返した。
あの黒い鋼鉄のような都市は伊達じゃない。
周囲のあらゆる環境から身を守るため厳重に封鎖されている。都市の人間がそこから出入りする為には宇宙飛行士並みのチェックを受けなくてはならない。自分たちの住んでいる環境の緩やかさとは大違いだ。
もちろんこの団地も外から飛来する火山灰や放射線、突然変異を来たしたウイルスの進入を遮る為に出入り口は二重のチェックで守られている。しかし、それは都市の比ではない。それほど高性能な文明の利器がないからだ。都市に比べたら随分原始的な生活をしているともいえるだろう。
ひとたび都市に移り住んでしまったら、再びここに戻ることはできない。
都市に移り住むということは一方的な片道切符なのだ。
「いや、いいんだよ、エレナ。今日会えただけでも嬉しいよ」
ミノルは心からそう言った。
そう、今日ここで再び懐かしい友人に会えるとは思ってもみなかったのだ。
ミノルは話題を変えようとした。
「そのスーツはセリグが開発したのかい?ニュースで見たぞ。今度のは随分高性能だって話だったけど、子供を抱きかかえるには問題があるようだな」
ミノルが先ほどの仕返しという顔をセリグにして見せると、セリグは降参したとでも言うように両手を挙げて見せた。
懐かしいその仕草を見てミノルとサラはまたもやくすくすと笑った。
「あなたはこのスーツに何でもかんでも盛り込みすぎなのよ。地上で生活する最低限のものを盛り込めばこんなに硬くならないのに」
エレナがぴしゃりと言った。
「いや、でも宇宙で活動することを考えると、これくらいの硬度は当たり前で、これでもまだ足りないくらいなんだ」
セリグはミノルに訴えた。
「宇宙…」
サラが突然顔をこわばらせた。
ミノルは思わずサラを振り返ったが、すぐに目を背けた。いい雰囲気だったのに全てぶち壊してしまった。
サラは辛抱強く大人たちの会話を聞いていたナミを数度あやすと、目を伏せた。
「ごめんなさい。セリグ、エレナ。あなたたちはミノルにその話をしに来たのよね。悪いけど、私とナミは席を外すわね。私たちはもう十分話したし、それにナミはもうお昼寝の時間だわ」
サラは早口でそう言うとナミを抱きかかえたまま、足早にリビングを後にした。
にぎやかな空間に突如沈黙が訪れた。
「すまん、ミノル。…その…サラはまだ怒っているのか?」
セリグがおずおずと口を開いた。
「いや、いいんだ。まあ、座ってくれ。せっかく来てくれたんだ。ゆっくりと話をしよう」
ミノルは二人にソファを促した。
再会の喜びですっかり考えが回らなかったが、サラの言う通りだ。
大変な苦労をして都市からわざわざここまでやって来たんだ。単なるご機嫌伺いに来たわけではない。十五年ぶりに来たからにはそれなりに重い使命を背負ってやって来たはずなのだ。
そしてそれは宇宙―Z計画に関係することに違いない。
ミノルは真剣な面持ちで改めて二人に対峙した。